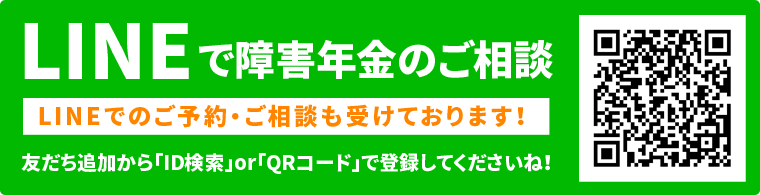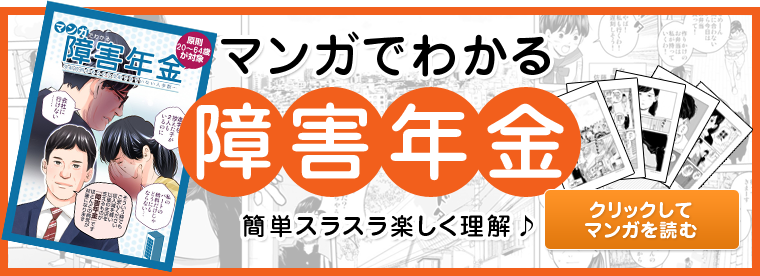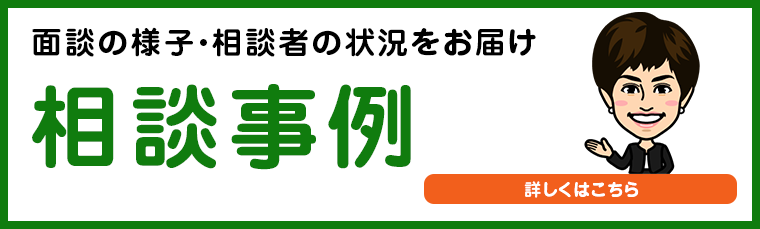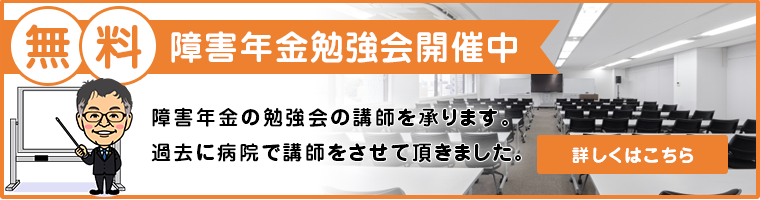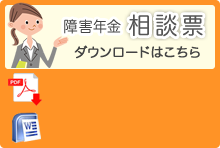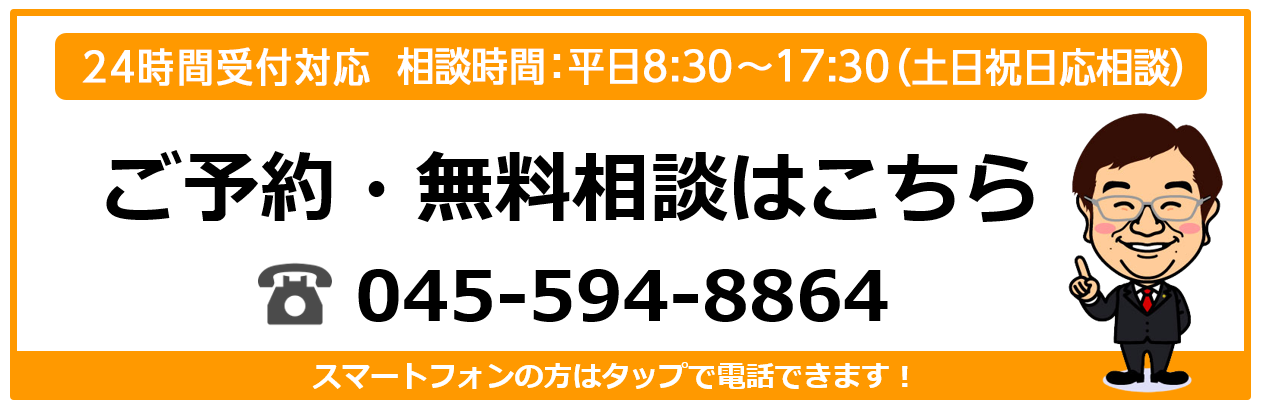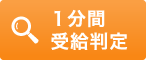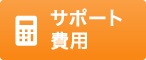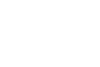最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
☆できること
1.幅広い傷病に対応可能です。

当事務所は、障害でお困りの多くの方に障害年金を受給していただきたいとの思いから、
当初より特に専門分野を設けずに、様々な傷病に対応してきました。
今日に至るまで年金機構が用意している全ての診断書で請求した実績もあります。
もちろんまだ私達が知らない傷病は沢山あると思います。
特に難病は初めて聞くような傷病名もありますが、
障害年金は傷病名で受給が決まるわけではありません。
その傷病によって日常生活や労働にどう影響しているかが問われますので、
どの診断書を選択し、どのように書いてもらうかがポイントになります。
当事務所はこの点をしっかり押さえ、どの傷病でも対応できる仕組みを整えています。

2.審査請求や再審査請求も行っています。
申請された書類を審査するのは日本年金機構によって選任された「認定医」と呼ばれる方たちです。
医師免許を持ち見識優れた方達なのですが、人間ですので
同じ障害認定基準を用いても診断書を厳しげに診る方がいれば、緩やかに診る方もいらっしゃるのは否めません。
それは個人差としても、時には決定された理由がどう見ても納得できない場合があります
(「家族としかコミュニケーションがとれない」という診断書の記述に対し、
「家族とコミュニケーションがとれているなら社会的に自立している」とされたことがありました)。
この様な時は「審査請求」や「再審査請求」で不服申し立てを行うことができます。
しかしこの不服申し立ては通常の裁定請求と異なり、申請の趣旨とその理由を文書にて申立てなければなりません。
そこには決定を覆すだけの理由と論理的な文章の組み立てが必要になりますが、
独特の文章構成が必要になり難しい作業になっています。
また一旦決まった決定を覆すという行為なのでそう簡単にはいきません。
苦労して申し立てても報われない(報酬を請求できない)場合が多いので、
やりたがらない社労士が相当数いるのも事実です。
ただやりたくないとは言えないので、
不服申し立ての報酬を他の社労士事務所の報酬より高めに設定して依頼が来ないようしているパターンが多いのです。
当事務所では困っている方のお力になれるよう、その様な事は行っていませんので、ご相談いただければと思います。
3.審査を考慮に入れた申請を行っています。
単純に障害年金の申請を行うだけなら、必要な書類を集めて提出すれば手続き的には完了します。
しかし、診断書を読み込むとその内容に疑義が生じそうな場合や、
病歴だけでは診断書の内容を補完しきれない場合も生じてきます。

その様な状態で提出すると内容に不備又は疑義があるとして「返戻」され審査に長期間を要したり、
最悪の場合「却下」や「不支給」となってしまいます。
当事務所ではそのような事態を極力避ける為、
審査の立場に立って不明な部分や疑義が生じる部分を潰してから申請を行うようにしています。
それにより決定までの期間が長期間にならずに済んだり、不服申し立てを行う必要がなくなるからです。
☆できないこと
1.診断書の内容について医師と交渉を行うこと

御依頼者様で、「診断書の内容について自分ではうまく医師と話せないので、
代わりに医師と交渉を行ってほしい」とご希望される方がいらっしゃいます。
しかし診断書は医師が医学的見地に基づき作成するものですので、
誠に恐縮ですが医師免許を持たない我々が診断書の内容についてあれこれ口を差し挟むことはできないのです。
もちろん、記入必須欄が空白だったり、間違った内容が書かれている場合は、直接医師に修正をお願いをしたり、
ご本人に対する事前ヒアリングと診断書の内容に齟齬が生じている場合に、医師に見直しをお願いすることはありますが、
総合判定(2)を(3)に変えてほしいですとか、
「できる」部分を「できない」に変えてほしい
という交渉はできないのです。
2.報酬のディスカウント
ごく稀ではありますが、
「2級なら2か月分支払うが、3級だったら1か月分にしてほしい」ですとか、
「報酬は〇〇円になりませんか」という
報酬のディスカウントのご要望を頂くことがありますが、
こちらに関しては残念ですがお応え致しかねます。
当事務所では賃料を支払って事務所を借りておりますし、給料を支払って職員にお仕事をしてもらっています。
報酬を下げるという事はこういった経費を賄えなくなる可能性があり、
下手をしたら事務所運営自体ができなくなります。
そうなりますと障害でお困りの方のお力になれなくなりますので何卒ご理解の程お願い致します。
3.障害認定日以外で遡及請求を行うこと

初診日から1年6か月後を障害認定日と言いますが、
遡及請求(遡って申請を行うこと)は障害認定日から3か月以内の日付の診断書を添付する必要があります。
ただこの期間に
受診していなかったり、
症状が軽かったり、
カルテが無い(廃院している)
と診断書の入手は不可能です。
しかし御相談者の中には、
「2番目の病院にはカルテが残っているから初診から2年後の診断書で申請して下さい」ですとか、
「障害認定日から1年後はすごく具合が悪かったので、この時点で認定日請求をお願いします」
といったご希望を受ける場合がありますが、
障害年金は障害認定日から3か月以内と現時点でしか障害状態を判断しませんので、
そういったご希望は一切受け付けられないのです。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!